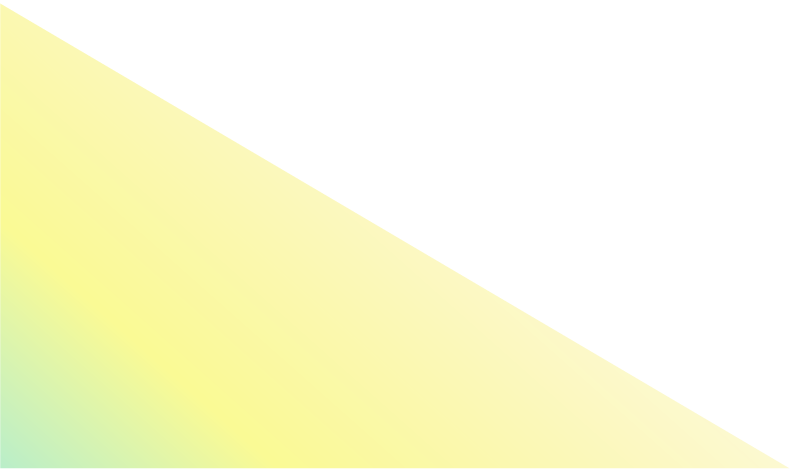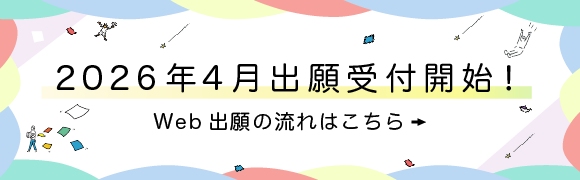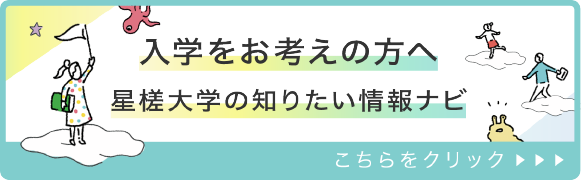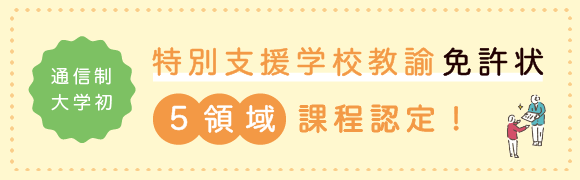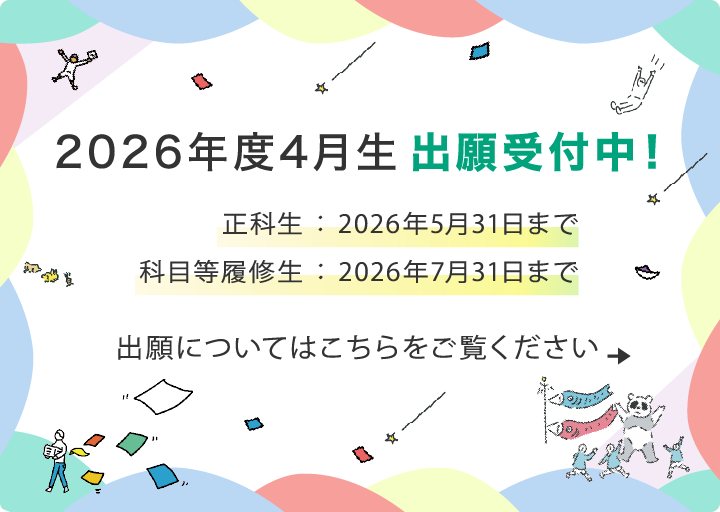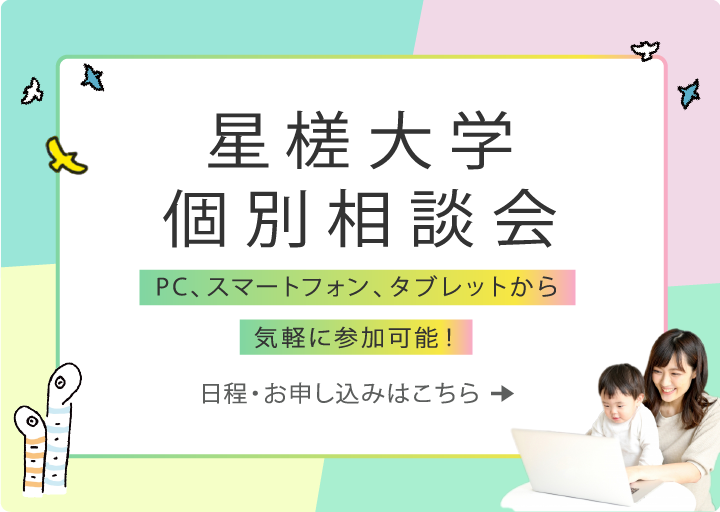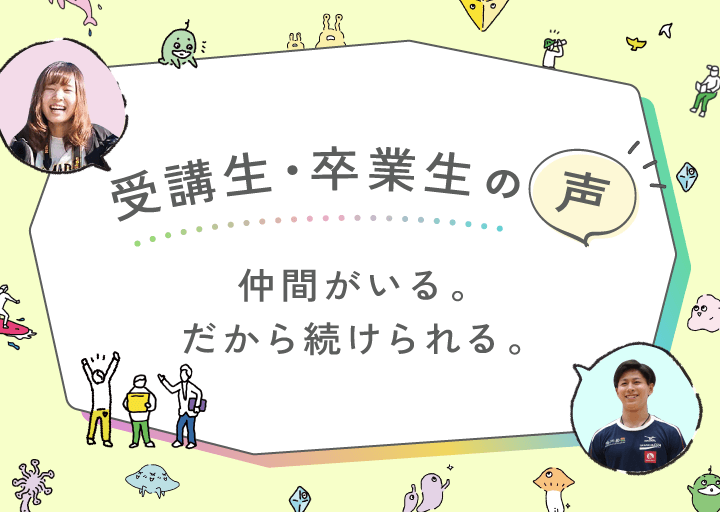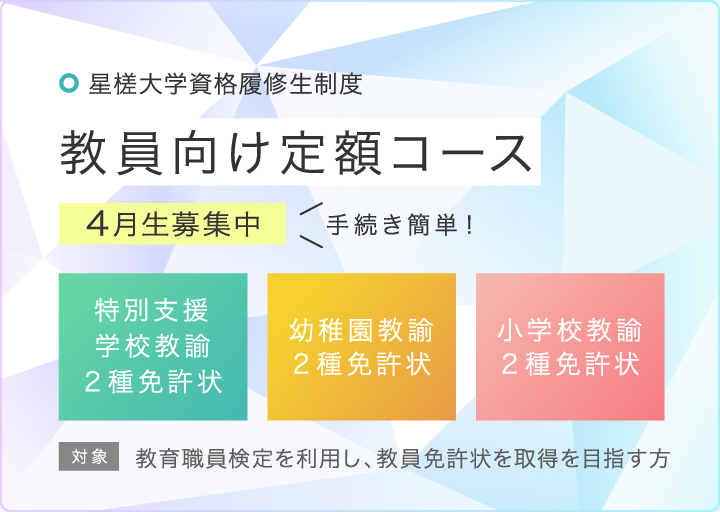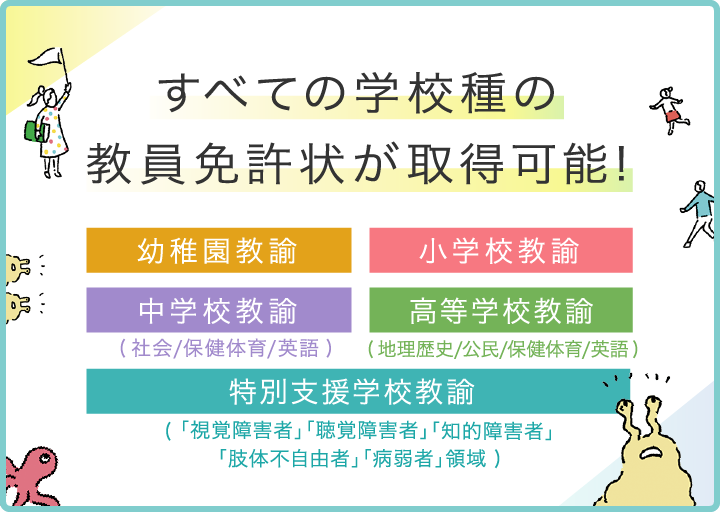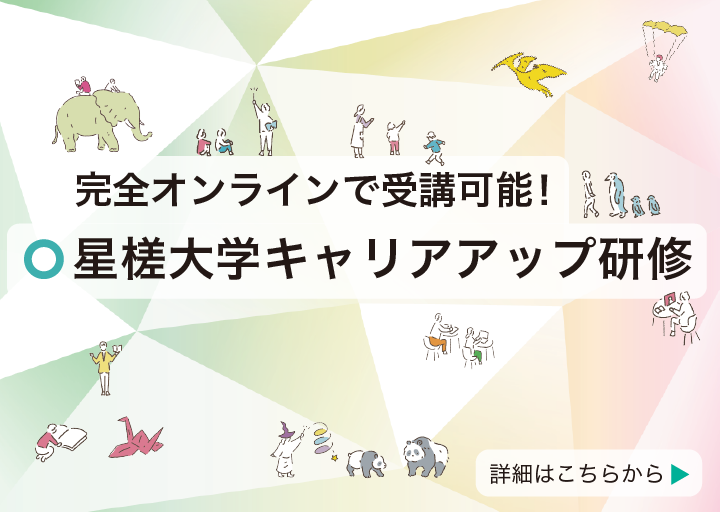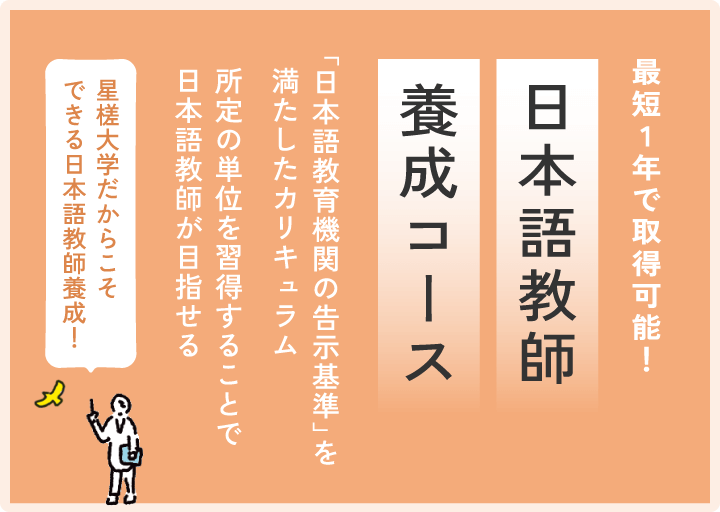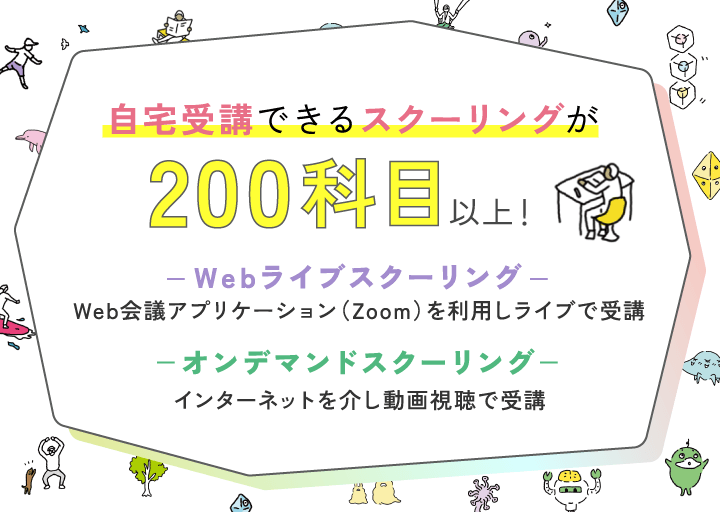- 教育
教育に求められる教師の役割とは? 一寸法師から学ぶ新しい教育観
話

星槎大学准教授
古壕 典洋(コボリ ノリヒロ)
専門分野:社会教育学、生涯学習論、遠隔教育論
プロフィール・研究業績等
現代教育において、教師の役割は大きく変化しています。従来の「教える側」から「支える側」へと転換し、学習者一人ひとりの個性や成長を大切にする教育が求められています。
本記事では、誰もが知る「一寸法師」の物語を教育学的視点から分析し、そこから見える新しい教育観や教師の役割について解説します。
答えのない問いに向き合う「ネガティブケイパビリティ」の重要性や、学習者中心の教育アプローチなど、現代教育に必要な考え方を具体的に紹介していきます。
教育学から見た一寸法師の教育的価値
物語に隠された教育的メッセージ
一寸法師という昔話を教育学の視点で見直すと、様々な教育的価値が見えてきます。
この物語は単なる娯楽ではなく、教育における本質的な問題を私たちに投げかけているのです。物語の中で一寸法師は小さな体で鬼を退治し、最後に大きくなって幸せになります。
しかし、なぜ物語は「大きくなる」ことで終わるのでしょうか。一寸法師の真の価値は、その小ささを活かした勇敢な戦いにあったのではないでしょうか。この疑問こそが、現代教育における重要な示唆を含んでいます。
昔々、おじいさんとおばあさんが子どもを授かりたいと、神社に通い願い続けた結果、小指ほどの小さな子どもが生まれました。
この子が一寸法師と名付けられ、いつまでたっても大きくならないものの、武芸に励み、家事を手伝い、やがて都へ修行の旅に出ました。都で貴族に仕え、娘と出会い、鬼を退治した後に、打ち出の小槌で大きくなって結婚し、幸せに暮らしたという物語です。しかし、この物語を教育学的に分析すると、多くの疑問が浮かび上がってきます。
大きくなることの意味を問い直す
一寸法師の物語で最も不思議な点は、なぜ「大きくなる」ことで物語が終わるのかということです。
一寸法師は小さいままでも十分に勇敢で、鬼を退治するという偉業を成し遂げました。むしろ、その小ささを活かして鬼の口の中に入り、内部から攻撃するという戦略は、彼の個性を最大限に活用したものでした。それにも関わらず、物語の結末で「大きくなった」ことが幸せの象徴として描かれているのは、教育的観点から見ると疑問に感じます。
この点について考えると、物語が作られた時代背景や社会的価値観が影響していることが分かります。
当時の社会では、物理的な大きさや力が重視される傾向があり、小ささは克服すべき欠点として捉えられていました。しかし、現代教育では、個々の特性や個性を尊重し、それぞれの強みを活かす教育が重要視されています。一寸法師の物語を現代的に解釈するなら、彼の小ささは欠点ではなく、他の人にはない独特の能力として評価されると考えられます。
自分らしさと成長の両立
一寸法師の物語から考える教育的価値として、「自分らしさ」と「成長」の関係があります。物語の中で一寸法師は、体が大きくなったことを「立派になった」と表現されていますが、これは一体どういう意味なのでしょうか。
小さいままでも十分に勇敢で立派だったのではないでしょうか。この「立派になった」という表現は、外見的な変化を価値とする社会的な価値観を反映しているように思われます。
現代教育では、学習者の「ありのまま」を受け入れることと、成長を促すことの両立が求められています。
一寸法師の視点に立って考えると、彼にとって小ささはどのような意味を持っていたのでしょうか。それは乗り越えるべき障害だったのか、それとも彼独自の特性だったのか。教育者としては、学習者の個性を尊重しながら、その人らしい成長を支援することが重要です。画一的な成長モデルではなく、多様な成長の形を認める教育環境の構築が必要なのです。
現代教育における教師の役割の変化
従来の「教える側」から「支える側」へ
教育学において最も重要なのは、教える側の発想から一旦離れることです。
教師は基本的に「おせっかい」な存在であり、「あなたのために」という言葉を頻繁に使います。しかし、この「あなたのために」が時として学習者にとって負担となったり、強制となったりすることがあります。現代教育では、教師が主人公ではなく、学習者が主人公であることを認識し、学習者の視点に立った教育を実践することが求められています。教師の役割は、知識を一方的に伝える存在から、学習者の学びを支援し、促進する存在へと変化しているのです。
従来の教育では、教師が知識を持つ者として、学習者に一方的に情報を伝達する形式が主流でした。
しかし、現代社会では情報へのアクセスが容易になり、知識の伝達だけでは十分ではなくなっています。教師に求められるのは、学習者が自ら学び、考え、判断する力を育成することです。これは、一寸法師の物語で言えば、彼の小ささを欠点として「治療」するのではなく、その特性を活かした成長を支援するような教育アプローチと言えるでしょう。
学習者の主体性を重視する教育
現代教育では、学習者の主体性を重視することが重要視されています。教師は学習者の興味や関心、学習スタイルを理解し、それに応じた学習環境を提供することが求められています。
これは、一寸法師が自ら都へ修行に出ることを決意したように、学習者自身が学習の目標を設定し、主体的に取り組むことを支援する教育です。
学習者の主体性を育むためには、教師は指導者としての役割だけでなく、学習の促進者、支援者としての役割も果たす必要があります。
学習者が自分の興味や関心に基づいて学習を進められるよう、適切な資源や機会を提供し、必要に応じて助言や支援を行います。また、学習者が自分の学習過程を振り返り、自己評価できるような環境を整えることも重要です。
おせっかいな教育からの脱却
教育者は往々にして「おせっかい」な存在になりがちです。
「あなたのために」という言葉を使って、学習者の将来を心配し、様々な指導や助言を行います。しかし、この「おせっかい」が時として学習者の自主性や創造性を阻害することがあります。現代教育では、学習者の自律性を尊重し、適切な距離を保ちながら支援することが求められています。
おせっかいな教育からの脱却には、教師自身の意識改革が必要です。教師は自分の価値観や経験を学習者に押し付けるのではなく、学習者が自分なりの価値観や判断基準を形成できるよう支援することが重要です。
これは、一寸法師の物語で言えば、彼の小ささを社会的な基準に合わせて「修正」するのではなく、その個性を活かした独自の道を歩むことを支援するような教育アプローチです。
学習者中心の教育アプローチとその重要性
学習者の視点に立った教育設計
教育学で最も大切にすべきは、学習者の視点です。「どう教えるか」や「どうしたら効率的か」ではなく、学習者が今何を考え、どんな思いがあり、どんな立場にいるのかを理解することが重要です。
学習者中心の教育アプローチでは、一人ひとりの学習者の個性や特性を尊重し、それぞれのペースに合わせた学習環境を提供します。これは、一寸法師の物語で言えば、彼の小ささを欠点として捉えるのではなく、その特性を活かした成長を支援するような教育と言えるでしょう。
学習者の視点に立った教育設計を行うためには、まず学習者の現在の状況を正確に把握することが必要です。
学習者の知識レベル、学習スタイル、興味や関心、学習に対する動機などを理解し、それに基づいて適切な学習内容や方法を選択します。また、学習者の文化的背景や生活環境も考慮に入れ、多様性を尊重した教育環境を構築することが重要です。
個々の学習者のニーズへの対応
学習者中心の教育では、個々の学習者のニーズに対応することが重要です。一人ひとりの学習者は異なる背景、能力、興味を持っており、同じ教育内容でも異なる反応や理解を示します。
教師は、これらの個人差を認識し、それぞれの学習者に適した学習機会を提供する必要があります。
個別のニーズに対応するためには、多様な学習方法や評価方法を用意することが重要です。視覚的な学習を好む学習者には図やグラフを用いた教材を、聴覚的な学習を好む学習者には音声や音楽を取り入れた教材を提供します。
また、学習の進度も個人差を考慮し、それぞれのペースで学習を進められるような柔軟な環境を整えることが必要です。
教室の主人公は学習者である
教室において真の主人公は教師ではなく、学習者です。この認識は、教育の根本的な考え方を変える重要な視点です。教師は学習者の学びを支援し、促進する役割を担っていますが、学習の主体は常に学習者自身にあります。教師は、学習者が自分の学習に責任を持ち、主体的に取り組めるような環境を整えることが求められています。
学習者が主人公となる教室では、学習者の声が重視され、彼らの意見や考えが教育活動に反映されます。教師は一方的に知識を伝達するのではなく、学習者との対話を通じて学習を深めていきます。また、学習者同士の協働や相互学習も重要な要素となり、多様な視点や考え方を共有することで、より豊かな学習体験が実現されます。
ネガティブケイパビリティと教育の関係
答えのない問いに向き合う力
従来の教育では、ポジティブケイパビリティ、つまり「できないよりはできた方がいい」「わからないよりはわかった方がいい」という向上する能力を重視してきました。しかし、現代教育では「ネガティブケイパビリティ」という概念が注目されています。
これは、答えが明確でない状況や、もやもやした状態に向き合う力のことです。日常生活のほとんどは答えが出ないことが前提であり、この中途半端でいることや、わからないことに向き合う力こそが、学習において最も大切な要素の一つなのです。
ネガティブケイパビリティは、不確実性や曖昧さを受け入れ、それらと共存する能力を指します。
一寸法師の物語についても、なぜ大きくなって終わるのか、立派になったとはどういう意味かなど、明確な答えのない問いがたくさんあります。このような問いに対して、すぐに答えを求めるのではなく、問い自体を大切にし、様々な視点から考え続けることが重要です。
もやもやを大切にする教育
教育において、「もやもや」した状態は決してネガティブなものではありません。むしろ、このもやもやこそが学習の出発点となり、創造性や批判的思考力を育む重要な要素となります。
学習者がもやもやした状態に遭遇した時、教師はすぐに答えを提供するのではなく、そのもやもやを大切にし、学習者が自分なりの理解や解釈を構築できるよう支援することが重要です。
もやもやを大切にする教育では、学習者の疑問や困惑を価値あるものとして扱います。教師は学習者の「わからない」という状態を問題として捉えるのではなく、学習の機会として活用します。また、学習者同士でもやもやを共有し、一緒に考えることで、多様な視点や考え方に触れることができ、より深い学習が実現されます。
ポジティブケイパビリティとの違い
ポジティブケイパビリティとネガティブケイパビリティの違いを理解することは、現代教育において重要です。
ポジティブケイパビリティは、明確な目標に向かって能力を向上させる力であり、従来の教育で重視されてきました。一方、ネガティブケイパビリティは、不確実性や曖昧さと共存する力であり、答えのない状況でも思考を停止させずに考え続ける能力です。
現代社会では、両方の能力が必要とされています。技術的なスキルや知識の習得にはポジティブケイパビリティが重要ですが、複雑で変化の激しい社会において創造的な解決策を見つけるためには、ネガティブケイパビリティも同じく重要です。教育者は、これら両方の能力をバランスよく育成することが求められています。
個性を活かす教育実践のあり方
ありのままを受け入れる教育
教育学では「自分らしさを大切に」「ありのままを重要だよね」「認めてあげる」ことを大切にします。しかし、「そのままを受け入れる」ことと、学習者が「変わっていく」ことの両立は簡単ではありません。
一寸法師の物語から考えると、彼の自分らしさとは何だったのでしょうか。小さいままでいることなのか、それとも大きくなることなのか。現代の教育実践では、学習者の個性を尊重しつつ、その人らしい成長を支援することが求められています。画一的な教育ではなく、多様性を認める教育環境の構築が必要です。
ありのままを受け入れる教育では、学習者の現在の状態を否定することなく、その人の持つ特性や能力を理解し、尊重します。これは、一寸法師の小ささを欠点として「修正」するのではなく、その個性を活かした独自の道を歩むことを支援するような教育アプローチです。教師は、学習者の多様性を認め、それぞれの個性が発揮できる環境を整えることが重要です。
変化と成長のバランス
個性を活かす教育において、「変化」と「成長」のバランスを取ることは重要な課題です。
学習者の個性を尊重することと、成長を促すことは時として矛盾するように見えることがあります。しかし、真の成長とは、個性を否定することではなく、その個性を基盤として新たな可能性を開拓することです。
一寸法師の物語を例に取ると、彼の成長は単に物理的に大きくなることではなく、自分の特性を活かして困難を乗り越える力を身につけることだったのかもしれません。
教育者は、学習者の個性を理解し、その個性を活かした成長の道筋を一緒に探求することが重要です。画一的な成長モデルではなく、多様な成長の形を認める教育環境の構築が必要です。
多様性を認める教育環境
現代教育では、学習者の多様性を認め、それぞれの個性が発揮できる教育環境を構築することが重要です。これは、文化的多様性、学習スタイルの多様性、能力の多様性など、様々な側面での多様性を含みます。教師は、これらの多様性を理解し、すべての学習者が安心して学習できる環境を整えることが求められています。
多様性を認める教育環境では、異なる背景や能力を持つ学習者が相互に学び合う機会が提供されます。これにより、学習者は自分とは異なる視点や考え方に触れることができ、より豊かな学習体験を得ることができます。また、自分の個性や特性を理解し、それを活かした学習方法を見つけることができるようになります。
教師が持つべき新しい視点と姿勢
学習者の立場に立つ重要性
教師が持つべき新しい視点として、学習者の立場に立つことの重要性が挙げられます。一寸法師の物語を例に取ると、おじいさんおばあさんの立場、娘さんの気持ち、そして鬼の視点など、様々な立場から物語を見ることで、全く異なる解釈が生まれます。
教師は固定観念から脱却し、柔軟な思考を持つことが必要です。また、学習者の成長を支援するために、その人の現在の状況や気持ちを理解し、適切なサポートを提供する姿勢が求められています。
学習者の立場に立つということは、教師自身の価値観や経験を一旦脇に置き、学習者の視点から物事を見ることを意味します。
これは簡単なことではありませんが、真の教育的支援を行うためには不可欠な能力です。教師は、学習者が直面している困難や課題を理解し、その人にとって最適な学習機会を提供することが重要です。
固定観念からの脱却
現代の教師には、固定観念から脱却する柔軟性が求められています。従来の教育では、特定の学習方法や評価基準が絶対的なものとして扱われることがありましたが、現代では多様な学習スタイルや能力が認識されています。
教師は、自分の経験や知識に基づく固定観念を見直し、常に新しい視点を受け入れる姿勢を持つことが重要です。
固定観念からの脱却には、継続的な学習と自己反省が必要です。教師は、学習者から学ぶ姿勢を持ち、自分の教育実践を常に見直し、改善していくことが求められています。また、他の教師や専門家との協働を通じて、新しい視点や方法を学び、自分の教育実践に活かすことも重要です。
柔軟な思考の育成
教師が柔軟な思考を持つことは、学習者の柔軟な思考を育成するためにも重要です。一寸法師の物語のように、一つの物語に対しても様々な解釈や見方があることを理解し、それらを学習者と共に探求することで、批判的思考力や創造性を育むことができます。
教師は、正解を教えるのではなく、学習者が自分なりの答えを見つけられるよう支援することが重要です。
柔軟な思考の育成には、多様な視点や考え方を紹介し、学習者がそれらを比較検討できる機会を提供することが重要です。また、学習者の異なる意見や考えを尊重し、それらを学習の資源として活用することも大切です。
教師は、学習者が安心して自分の考えを表現できる環境を整え、建設的な議論や対話を促進することが求められています。
地域と連携した教育実践の可能性
学校外での学びの機会
現代教育では、学校の枠を超えた教育実践が重要視されています。地域に出て行き、地域づくりや自分づくりを通じた学習は、学習者にとって貴重な経験となります。例えば、ものづくりを通した自分づくりや、地域の文化や自然を活かした学習活動は、学習者の主体性を育み、実践的な学びを提供します。また、多世代との交流を通じて、学習者は様々な視点や価値観に触れることができ、より豊かな学びを得ることができるのです。
学校外での学びの機会は、学習者に現実社会とのつながりを感じさせ、学習の意味や価値を実感させる効果があります。教室での理論的な学習だけでなく、実際の現場での体験を通じて、学習者はより深い理解と実践的なスキルを身につけることができます。また、地域の人々との交流を通じて、コミュニケーション能力や社会性も育成されます。
地域づくりと教育の融合
地域づくりと教育の融合は、現代教育における重要なアプローチの一つです。学習者が地域の課題に取り組み、その解決に向けて学習を進めることで、学習の動機が高まり、実践的な能力が育成されます。また、地域の人々と協働することで、学習者は多様な視点や価値観に触れ、より豊かな学習体験を得ることができます。
地域づくりと教育の融合では、学習者が地域の一員として主体的に参加し、地域の発展に貢献することが重要です。これにより、学習者は自分の学習が社会に役立つことを実感し、学習に対する意欲を高めることができます。また、地域の人々からの評価やフィードバックを通じて、学習者は自分の成長を実感し、自信を深めることができます。
多世代との交流による学び
多世代との交流は、学習者にとって非常に価値のある学習機会を提供します。異なる世代の人々との交流を通じて、学習者は多様な人生経験や知識に触れることができ、自分の視野を広げることができます。また、世代間の価値観や考え方の違いを理解することで、多様性を尊重する態度を育むことができます。
多世代との交流による学びでは、学習者が単に知識を受け取るだけでなく、自分の考えや経験を伝える機会も提供されます。これにより、学習者は自分の学びを整理し、他者に分かりやすく伝える能力を育成することができます。また、異なる世代の人々から学んだことを自分の学習に活かすことで、より深い理解と実践的な能力を身につけることができます。
教育における「もやもや」の価値
不確実性を受け入れる力
教育において、すべての問いに明確な答えがあるわけではありません。むしろ、「もやもや」した状態こそが学習の出発点となることが多いのです。
一寸法師の物語についても、なぜ大きくなって終わるのか、立派になったとはどういう意味かなど、明確な答えのない問いがたくさんあります。このような問いに向き合うことで、学習者は批判的思考力を育み、創造性を発揮することができます。教師は、学習者の「もやもや」を大切にし、それを学習の機会として活用することが重要です。
不確実性を受け入れる力は、現代社会において非常に重要な能力です。変化の激しい現代社会では、明確な答えのない問題に直面することが多く、そのような状況において適切に判断し、行動する能力が求められています。教育者は、学習者がこのような不確実性と向き合い、それを乗り越える力を育成することが重要です。
批判的思考力の育成
「もやもや」した状態は、批判的思考力を育成する絶好の機会となります。学習者が疑問や困惑を感じる時、それは既存の知識や理解では説明できない状況に遭遇していることを意味します。このような状況で、学習者は自分の思考を見直し、新しい視点や考え方を探求することが必要になります。教師は、このプロセスを支援し、学習者が自分なりの理解や解釈を構築できるよう導くことが重要です。
批判的思考力の育成には、多様な視点や考え方を紹介し、学習者がそれらを比較検討できる機会を提供することが重要です。また、学習者が自分の考えを論理的に説明し、他者の意見を聞いて建設的な議論を行えるような環境を整えることも大切です。教師は、学習者が安心して自分の考えを表現できる雰囲気を作り、多様な意見を尊重する姿勢を示すことが求められています。
創造性を育む教育環境
創造性を育む教育環境では、「もやもや」した状態が歓迎され、それが新しいアイデアや発見の源泉として活用されます。学習者が既存の枠組みにとらわれず、自由に発想し、新しい可能性を探求できる環境を整えることが重要です。教師は、学習者の創造的な思考を評価し、支援することで、創造性の発達を促進することができます。
創造性を育む教育環境の構築には、学習者が失敗を恐れずに挑戦できる雰囲気を作ることが重要です。また、多様な学習方法や表現方法を提供し、学習者が自分に合った方法で学習を進められるような柔軟性も必要です。教師は、学習者の個性や創造性を尊重し、それぞれの独自性を発揮できる機会を提供することが求められています。
以上のように、一寸法師の物語を教育学的視点から分析することで、現代教育における重要な示唆を得ることができます。教師の役割は大きく変化しており、学習者中心の教育アプローチ、ネガティブケイパビリティの重要性、個性を活かす教育実践など、様々な要素が現代教育において求められています。教育者は、これらの視点を理解し、実践に活かすことで、より効果的で意義のある教育を提供することができるでしょう。