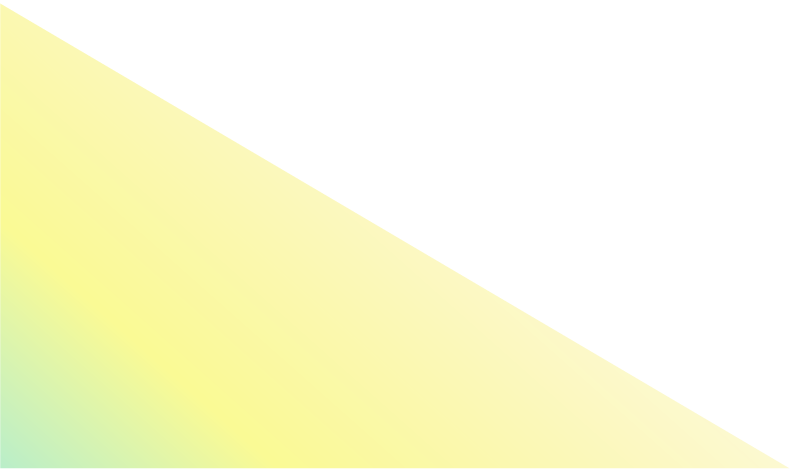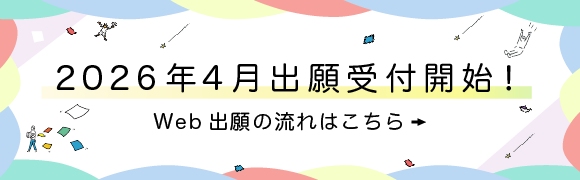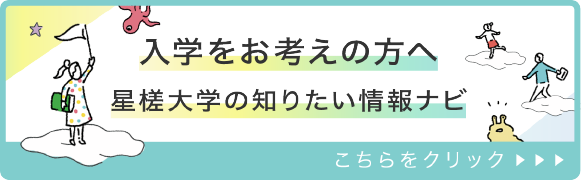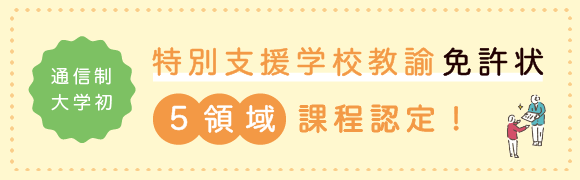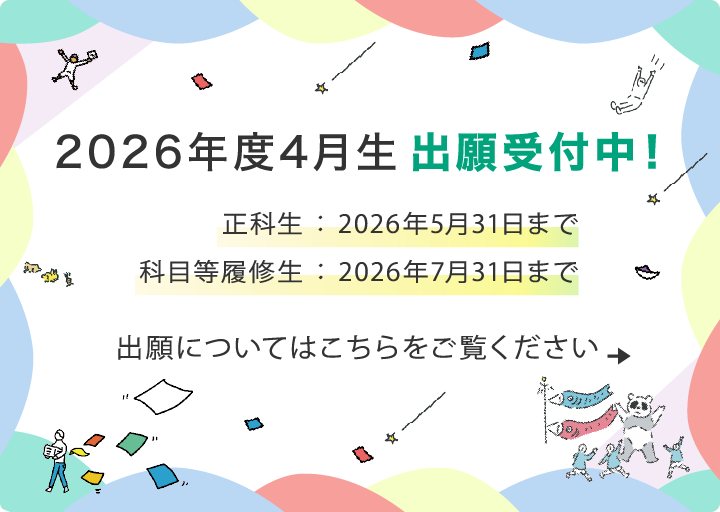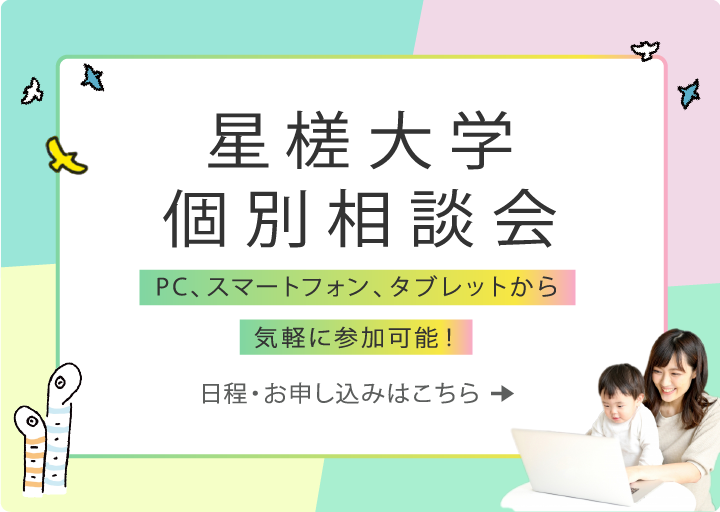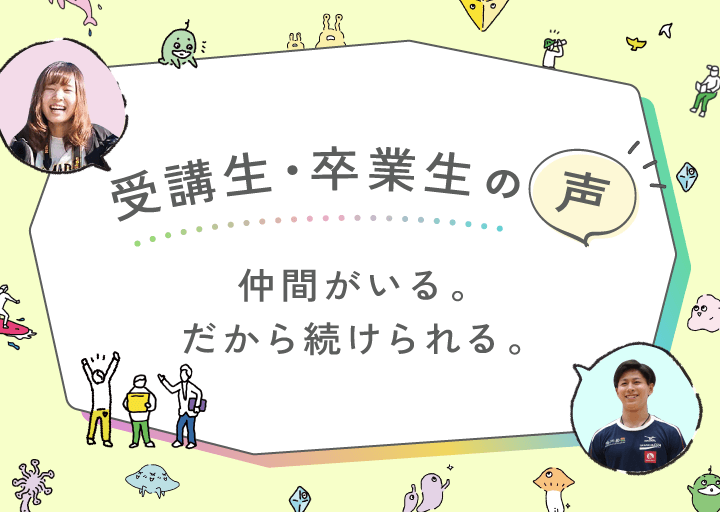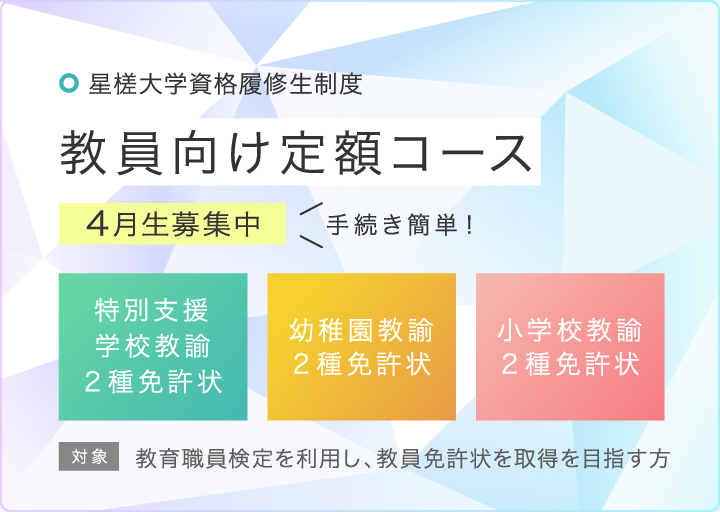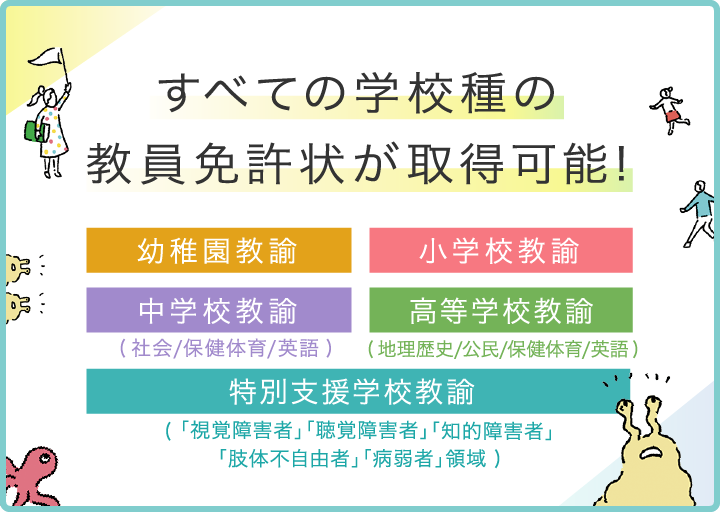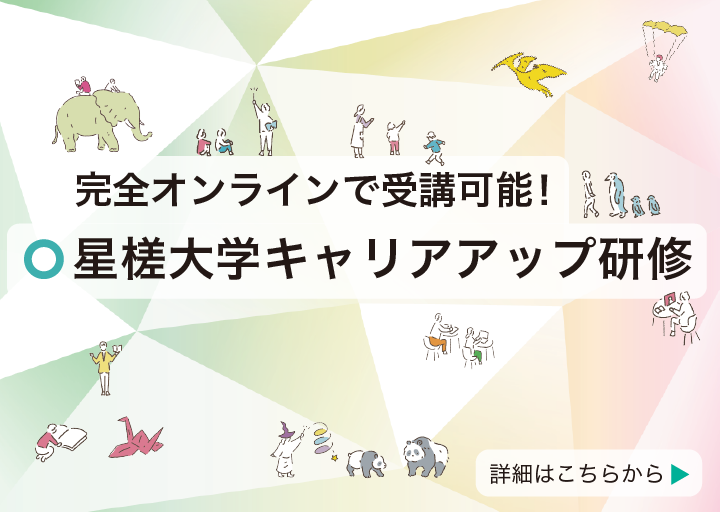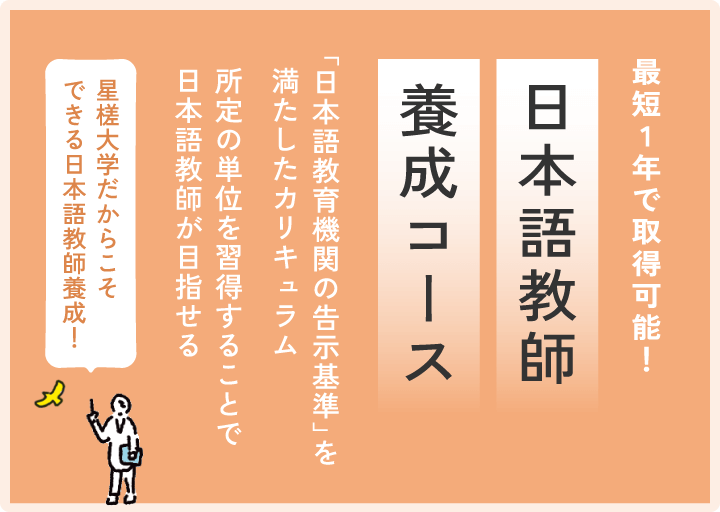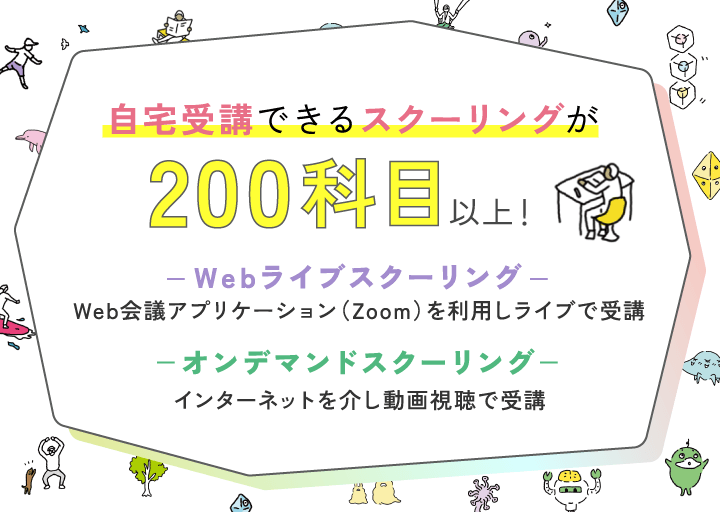- 教育
- 初等教育
- 中等教育
「教え・共に考え・学びあう」 ー 子どもに関わる教師の立ち位置 ー
学校の教育目標の具現化を目指して日々の教育活動を推進する、まずはそれが教育組織の一員として教員に期待されるところです。「学級」における「担任」としての子どもとの関わりには三つの局面があります。教師の立ち位置として考えてみましょう。
子どもと関わる三つの局面
一つ目は「教える」立場。「教える−教えられる」、非対称的な関係としての立ち位置です。子どもが登校して教室に入り、学習の準備をする、時間割に従って授業に臨む。「教室」をそのような「学びの場」として構成する指導には、ある種の「強制」を伴います。子どもがそれを受け入れることができるようにする局面といってよいでしょう。
二つ目には「共に考える」立場。学級においては自ずと子ども相互の関係が生じます。それを望ましい方向へと促すことができるかどうか。望ましい相互関係とはどのようなあり方か、それをどのように構築するか、子どもたちとともに考え、働きかける教師の立ち位置です。
ここでは、子ども それぞれの「主体性」を前提とする難しさが伴います。相互関係のあり様を子どもたちに委ねてしまえば、力関係が場を支配しかねません。「いじめ」が生じるのもこのような局面です。「指導」による制御が困難であり、子どもの「主体性」に相対する教師の立ち居振る舞いが問われるところです。
三つ目には「学びあう」立場。教師は「教えて」いるつもりでも、子どもは「主体的」に学んでいます。教師の期待に適うかどうかとは別に子どもは学んで(しまって)います。そのような子どもたちと共に、教育の理念が目指す学びを具現できるかどうか。教師の 「学び」が問われる一方、やりがいのある局面です。「個別最適な学び」と「協働的な学び」の「一体的な充実」を具現する上での課題でもあります。
子どもとどのように関わるかは難しいところですが、三つの局面を視野に、ともに学びあう場の構築を目指しましょう。
文

大隅 心平(オオスミシンペイ)
専門分野:学校・学級経営、特別活動、道徳教育、現代社会におけるこども論
プロフィール・研究業績等