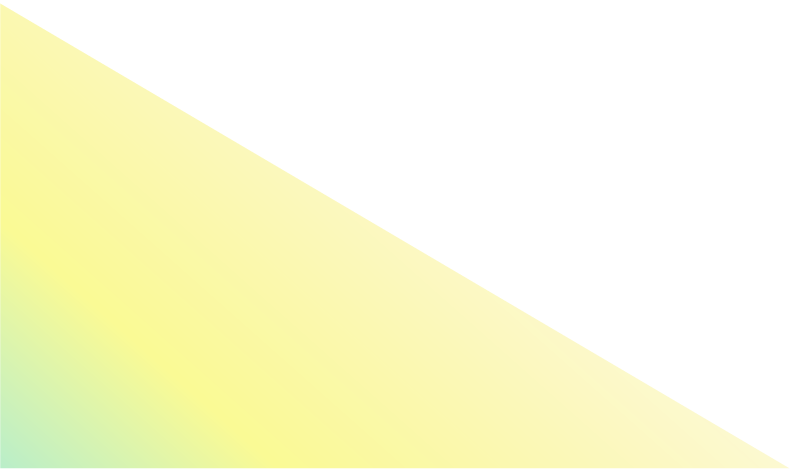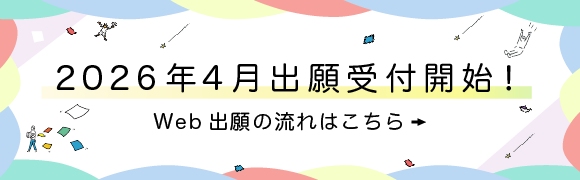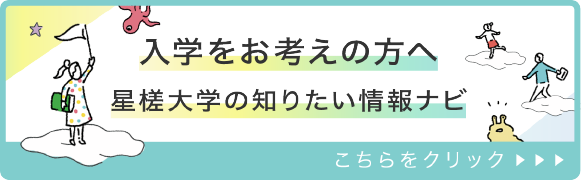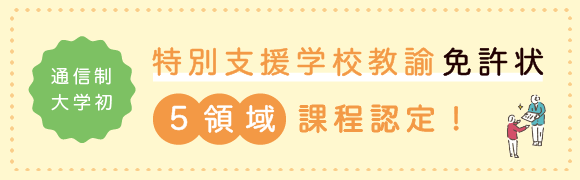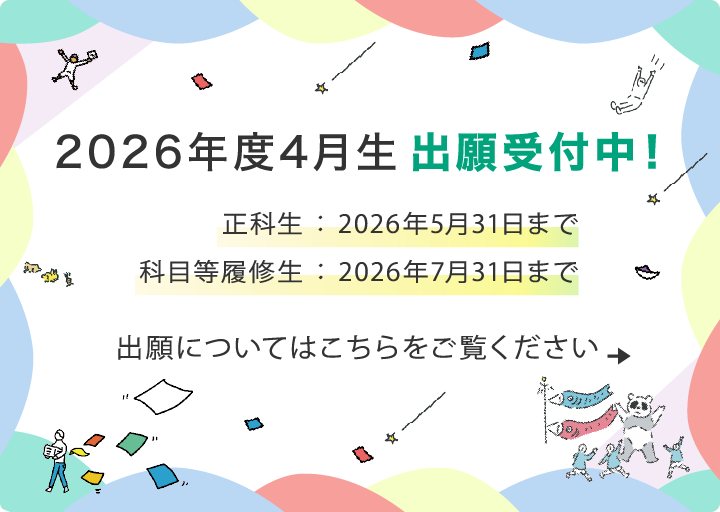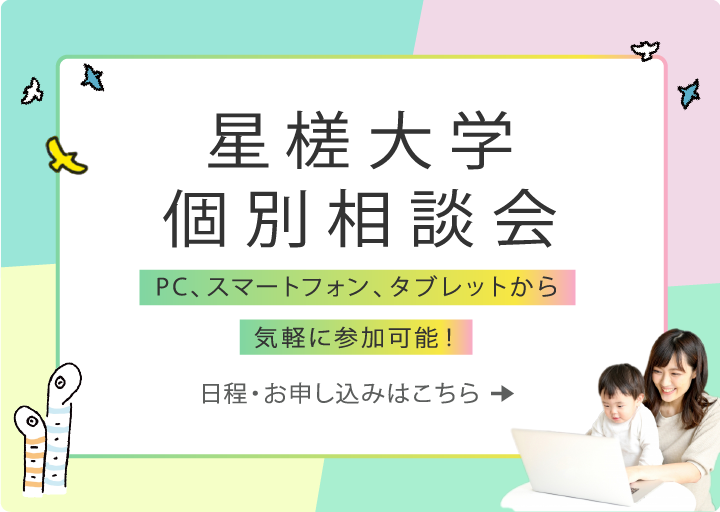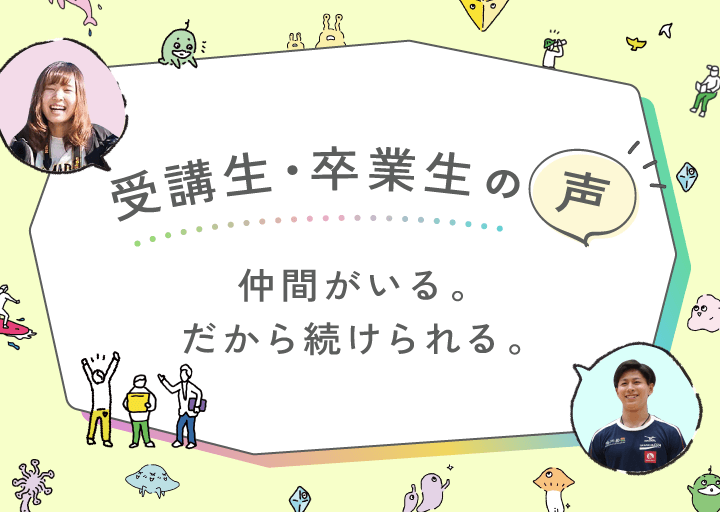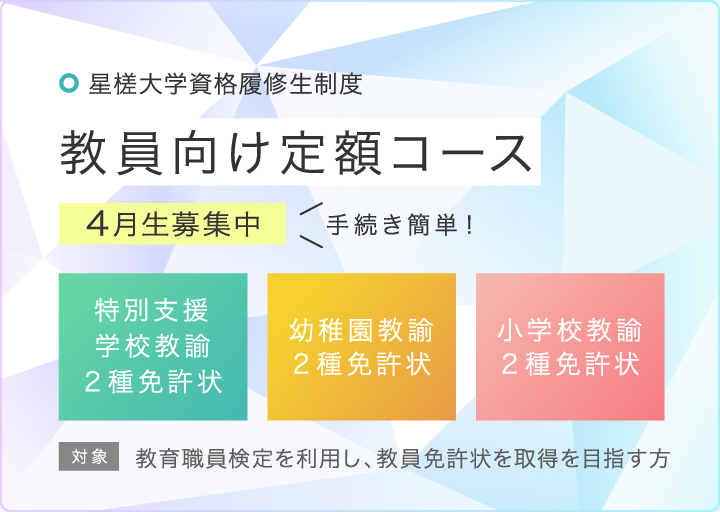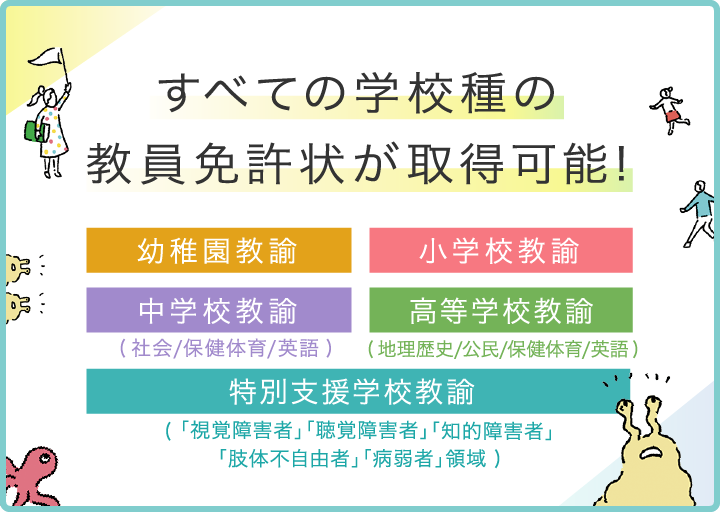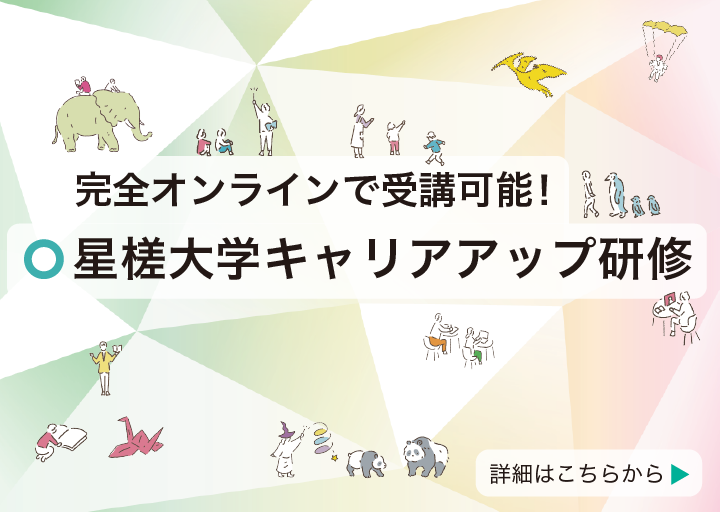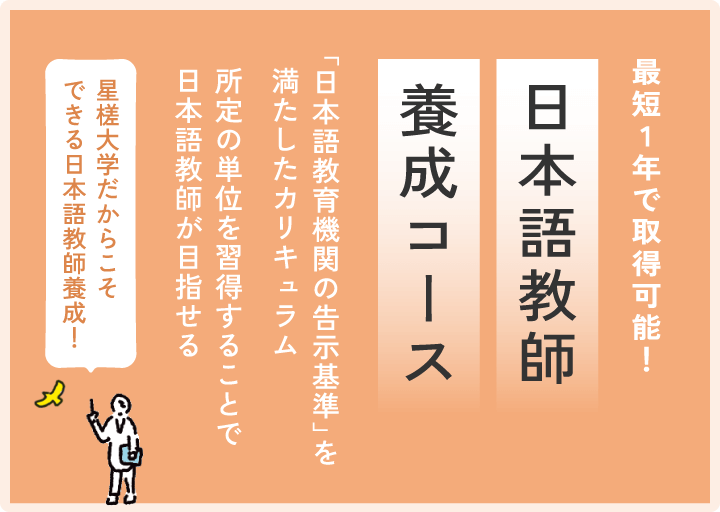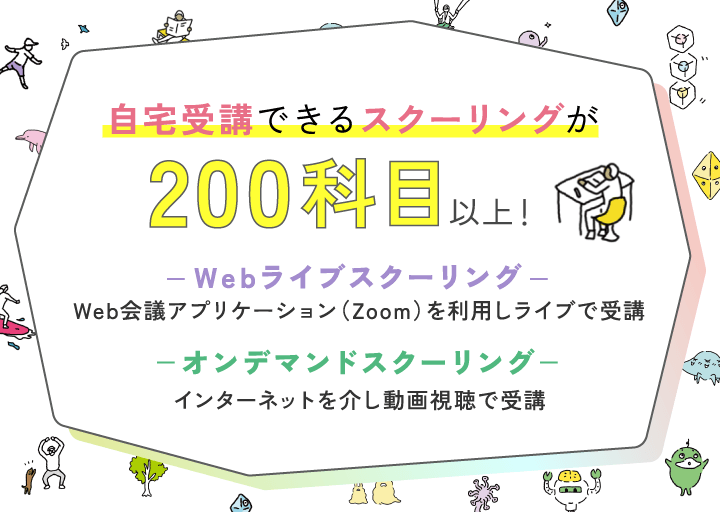- 教育
- 特別支援教育
成人期の発達障害といじめの後遺症
話

星槎大学教授
平 雅夫(タイラ マサオ)
専門分野:障がい児者の教育、障がい児者の心理、障がい児者の福祉
発達障害を抱える成人への支援は、社会の中でますます重要性を増しています。本記事では、成人期の発達障害者支援の現状、いじめの後遺症の実態、その影響を受けた方々への具体的なサポート策について解説します。これらの情報を通じて、支援者や関係者が今何をすべきか、未来に向けてどのようなアプローチが必要かを考える一助となれば幸いです。
成人期の発達障害者支援の現状と課題
成人期における発達障害者等への支援は、近年やっと注目され始めた分野です。発達障害を持つ方の多くは、学校や就労の段階で適切な支援を受けられず、社会生活の中で苦労を重ねています。実際に企業で働く発達障害者の中には、福祉サービスや医療支援に頼らずに社会に適応しているケースも多くあります。一方で、支援がなければ生活が成り立たないほど悪い状態に追い込まれる方もいます。その差を理解し、適切な対応を行うことが求められています。特に成人期の支援は、就労や地域生活の場において長期的かつ個別化されたアプローチが不可欠です。成人期になってから初めて支援の現場に相談に来る方々の多くは、すでに日常生活において深刻な困難を抱えていることが多いです。
支援における個別性の重要性
成人期の発達障害者支援では、一律の対応ではなく、それぞれの特性や生活環境、過去の経験を踏まえた個別支援計画が求められます。特に、就労場面における合理的配慮の提供や、職場環境の調整は、本人の能力を最大限に発揮するために不可欠です。また、医療機関、福祉機関、教育機関が連携し、包括的なサポート体制を構築することが、長期的な支援の成功につながります。地域社会全体での理解と協力が、支援を必要とする方々の社会参加を促進する基盤となるのです。
いじめの後遺症とその長期的影響
調査によると、成人期の発達障害者支援を受けている方々の中で、過去にいじめの被害に遭った経験を持ち、今もその影響を感じているという方が93%にも上るというアンケート結果があります。
実際に、いじめの後遺症に関する研究は国内では少なく、海外の研究結果を参考にしながらも、具体的な支援策の構築が求められています。特に、日本の教育現場や福祉制度においては、いじめの被害者へのフォローアップ体制の整備が急務です。イギリスの教育研究を中心に活動している滝沢(2014)らの研究によれば、7歳から11歳の間にいじめを受けた子どもが成人期に達した際、うつのリスクが1.95倍、不安障害のリスクが1.65倍、自殺のリスクが2.21倍に上昇するという結果が報告されています。
教育現場における継続的なフォローアップの必要性
現在の教育現場では、学年が変わるごとに担任が変わり、児童生徒の状況がリセットされてしまう傾向があります。また、卒業後の追跡調査や継続的なサポートの仕組みが十分に整備されていないのが現状です。例えば、小学校3年生でいじめの被害に遭い、不登校になった子どもが、4年生でクラス経営の上手な教師のもとで学校に通えるようになったとしても、いじめの後遺症が癒えたわけではありません。5年生になって再び不登校になった場合、いじめの後遺症による不安の高まりや、自己肯定感の低下、抑うつ状態が影響している可能性も考えられます。しかし、いじめの後遺症に関する認識が不足しているため、適切な対応がなされないケースが多く見られます。
心理的ケアと社会参加の促進
いじめや発達障害のサポートには、心理的ケアと社会参加の促進が欠かせません。心理的ケアでは、カウンセリングや心理療法を通じて、トラウマの癒しや自己肯定感の回復を図ります。さらに、自己理解や対人関係のスキルを向上させるためのプログラムも効果的です。
社会参加の促進については、就労支援や地域活動への参加を推奨し、本人の意欲と能力に合わせた支援を行います。具体的には、職場での合理的配慮や、地域の交流イベント、趣味のサークルなどが有効です。これらの取り組みは、自己肯定感を高め、社会への適応力を養うことに直結します。
また、支援者側も多職種連携を強化し、医療、福祉、教育が一体となったネットワークを構築する必要があります。特に、いじめの被害に遭った方々は、不安が高まりやすく、ネガティブな認知パターンに陥りやすいため、丁寧で継続的な心理的サポートが求められます。社会から孤立することは、中年期や高年期における更なる困難を招くリスクがあるため、早期の段階から包括的な支援を提供し、社会への適応と参加の意欲を維持していくことが重要です。
まとめ:支援の現場に求められること
発達障害やいじめの後遺症を抱える方々への支援は、社会全体の課題です。本人の尊厳を守りつつ、長期的かつ継続的な支援を行うことが求められます。特に、本人の声を丁寧に聴き、適切な支援策を講じることが、何よりも大切です。
私たち一人ひとりが、この問題に関心を持ち、行動を起こすことで、より良い社会を築くことができると信じています。発達障害やいじめの後遺症に苦しむ人々が、安心して社会に参加できる未来を実現しましょう。